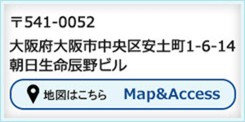017 眼刺激性試験 OECD TG492とOECD TG492Bは何が違う?
2025.10.9
皆さんが普段使っているスキンケア製品やヘアケア製品、使い方に気を付けていても誤って目に入ってしまうかもしれません。
この万が一の事態を見据えて実施するのが「眼刺激性試験」です。
製品に含まれる化学物質(原料)が眼に接触した際に、刺激や障害を引き起こすかどうかを評価します。

眼刺激性試験の歴史
最初に開発された眼刺激性試験はドレイズ試験です。
実験動物(ウサギ)を用いた試験で、1944年に開発されました。
しかし、動物への苦痛や動物愛護の観点や、EUを中心とした動物実験の禁止・制限の流れを受け、次第に細胞や三次元培養組織モデルを用いた動物実験代替法の開発が活発化しました。
現在は様々な動物実験代替の眼刺激試験法が開発され、OECDガイドラインとして認可されています。
眼刺激性試験 OECD TG492
OECD TG492は、2015 年にOECDガイドラインとして認可されたin vitro眼刺激性試験法です。
ガイドラインで認められているヒト由来の三次元培養角膜上皮モデル※を使用する必要があります。
ヒト由来モデルを使用するため、ヒト臨床での生体反応をより正確に反映できる点が特徴です。
眼刺激性の有無は、試験サンプル適用して一定時間後の細胞生存率から判定します。
細胞生存率を指標とするため、他の眼刺激性試験法と比較して試験可能なpH幅が広く、より多くの試験サンプルに適用できます。
※EpiOcular™、SkinEthic™ HCE、LabCyte CORNEA-MODE の 3 種類(2025 年 9 月時点)
眼刺激性試験 OECD TG492B
OECD TG492をベースに改良したのがOECD TG492Bで、2022年6月にOECDガイドラインとして認可されました。
OECD TG492と大きく異なる点は、ガイドライン採用モデルとGHS区分です。
まず、ガイドライン採用モデルに関して、OECD TG492では複数のメーカーから選択できますが、OECD TG492BはEPISKIN社のSkinEthic™ HCEのみとなっています(2025年9月時点)。
また、評価区分についても、眼刺激性ありorなしの2パターンでGHS区分外のみ分類できるOECD TG492に対し、OECD TG492Bは3区分です。
具体的には、「眼刺激性あり」が刺激の強さによって更に2つに区分されます。
このことから、OECD TG492は「眼刺激性がないことを確認する」ための試験法であるのに対し、OECD TG492Bは「眼刺激性の強さまで含めて分類する」ことができる試験法であると言えます。
表 GHS区分の比較
| 眼刺激性あり | 眼刺激性なし | ||
| OECD TG 492 | (GHS区分できない) | GHS区分外 | |
| OECD TG 492B | GHS区分1 | GHS区分2 | GHS区分外 |
OECD TG 492B唯一の採用モデル SkinEthic™ HCE

SkinEthic™ HCEは、フランスのEPISKIN社製造の三次元培養角膜上皮モデルです。
ヒト角膜上皮に類似した構造で、ムチン等の角膜に特異的なタンパク質の発現も観察されています。
近年は、眼刺激性試験OECD TG492やOECD TG 492Bの採用モデルとして、試験機関や化学メーカーからの需要が高まっています。
ニコダームリサーチは EPISKIN 社製造モデルの日本代理店です!
ニコダームリサーチはEPISKIN社と提携し、日本のお客様にEPISKIN社製造の三次元培養組織モデルを販売しています。
詳細はぜひ製品資料をご覧ください。
こちらのページから情報入力後、製品資料を閲覧・ダウンロードいただけます。