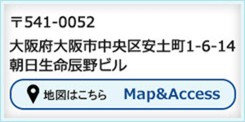006
化粧水の疑問
2025.1.31
今回のコラムは、「化粧水でよく耳にする噂」と「処方された最終製品で有用性評価を実施する意味」について解説します。
化粧水はほとんどが水でできている?
→ホント

市場に出回っている大半の化粧水は、9割以上が水で構成されています。
残りの1割未満に、水溶性の保湿成分(グリセリン、BG等)や訴求成分(美白、抗炎症等)、安定化成分(pH調整、防腐等)等が配合されています。
ほとんど水でできているなら、使っても効果はないの?
→ホントとは言い切れない

最近、「化粧水は使わない」「洗顔後、化粧水をスキップして美容液を使う」という美容関係者・インフルエンサーも耳にしますよね。
確かに、美容液と比較して化粧水は保湿成分や訴求性分の配合比率が少ないため、化粧水を使わないという人も一定数います。
しかし、ホントとは言い切れない理由があります。
① 肌のpHを整え、その後のスキンケアの効果を高める役割があるから
私たちの肌は通常、弱酸性(pH5~6)に保たれていますが、乾燥肌はアルカリ性に、脂性肌は酸性に傾いてしまいます。
そのため、肌トラブルを防ぐために弱酸性を保つことは重要で、化粧水がその役割を担うことが多いです。
また、洗顔後、まず化粧水で肌のpHを整えることで、その後のスキンケア(美容液や乳液、クリーム等)の効果を高める役割もあります。
② 訴求成分は微量配合でも効果を発揮することもあるから
例えば、水溶性成分であり抗炎症目的で配合されるグリチルリチン酸2Kを医薬部外品(薬用化粧品)として化粧水に配合する場合、配合量0.05~0.5%に収めなければなりません。
つまり、配合量0.05~0.5%でも効果を発揮するということです。
9割以上が水だとしても、残りの1割に含まれている訴求成分がしっかり効果を発揮することもあるため、一概に効果がないとは言い切れません。
有用性エビデンスデータを取得して、化粧水の価値を高めませんか?

化粧品の処方開発~最終製品化の工程は、奥深いですよね。
成分をどのように配合するかで、エンドユーザーが体感する肌への作用、使用感が大きく変わることもあるかもしれません。
時間を掛けて開発する製品―。
きっと様々な条件内でのベストを目指されていることと思います。
発売後に後悔しても、後戻りはできません。
だからこそ、上市前に、製品で有用性評価を行うことは、とても意義があることだと考えます。
ニコダームリサーチは、訴求成分がどの程度皮膚に浸透しているかを評価する「皮膚透過性試験」や「長期連用による肌状態評価」、「即時的な保湿・バリア機能の評価」等の受託を承っています。
有用性エビデンスデータ取得・評価をご検討中でしたら、お気軽にお問合せください。