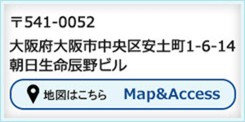012 解析担当者が解説!DNAマイクロアレイが拓く、素材開発の新たな可能性
2025.7.16
グループ会社の日光ケミカルズ 中央研究所の評価解析担当者であるNさんにDNAマイクロアレイについて解析していただきました。原料開発者がこの技術をどう活かすべきか、その視点からも深く掘り下げていますので、ぜひ最後までご覧ください!
DNAマイクロアレイは遺伝子の発現変動を網羅的に評価する手法のひとつです。ヒトの遺伝子は約23,000個あるとされており、現在ではほとんどの遺伝子変動を精度高く解析できるようになっています。
化粧品をはじめパーソナルケア等の有用成分はこれまでに非常に多くの種類が存在し、様々な機能性が探索されてきています。それゆえ、これから先、独自性がある有用成分の開発は容易ではありません。さらには刻々と変化する市場の動向に合わせたスピード開発が強いられており、ますます困難な状況となってきています。

- サステナブルな素材に有用性を付加したい
- 既存素材に新たな有用性を付加して、リニューアルしたい
- 化粧品素材として新規導入するために、評価したい
- 素材の有用性はわかっているが、細胞レベルのメカニズムが知りたい
以上は開発相談の一例ですが、共通しているのは未知の機能性を評価したいというところです。しかし限られた期間の中で手さぐりに新しい機能性を探索することは至難であり、たとえそのきっかけをつかんでも、その機能性が素材の真のポテンシャルかどうかはわからないところです。

素材の有用性を評価する第一ステップは培養細胞を使った評価がほとんどです。
皮膚領域で言えば、表皮角化細胞や真皮線維芽細胞を用いたin vitroアッセイが中心となります。これまでは機能性発現のカギとなる遺伝子やたんぱく質を対象に評価することが多く、定量PCR法やELISA法によって検討されています。
しかし、マーカー遺伝子のみを対象とした評価では本当の素材が持つポテンシャルが見えないことがあり、DNAマイクロアレイによる解析によってはじめて分かることがあります。
例えば、ヒト表皮角化細胞を用いたDNAマイクロアレイ解析から素材Aと素材Bの適用によってKRT1とKRT10の発現が増加した結果が得られました。
KRT1とKRT10はヒト表皮角化細胞における分化マーカーとして広く知られています。つまり、この結果からは素材Aと素材Bはともにヒト表皮角化細胞の分化を促進させる機能性に期待がかかります。一方で、皮膚バリア機能に重要なセラミド合成や細胞接着(タイトジャンクション)、プロテアーゼ関連因子に注目すると、DNAマイクロアレイが示す結果は素材Aの方がより多くの関連遺伝子に変動が大きく、素材Bは細胞接着(タイトジャンクション)関連遺伝子のみに変動があることがわかります (図1参照)。
つまり、素材Aはより角層に近い分化後期に大きく影響し、素材Bは分化初期に大きく影響していると考えられます。したがって、素材Aと素材Bは全く異なる機能性を持つことが期待されます。
皮膚における機能性は多くの遺伝子がかかわっています。遺伝子の動きを網羅的に観察することでその素材が持つポテンシャルはすべてオリジナルなものです。その“個性”を開発することは素材を真に生かすことにつながるのではないでしょうか。

機能グループは表皮角化細胞における機能に関連する遺伝子群を示しており、発現比の列の各枠が固有の遺伝子を表しています。発現比は対照コントロールと比較した遺伝子発現変動を示し、発現増加(緑グラデーション)、発現減少(赤グラデーション)、発現変化なし(白)で表しています。図に示した機能は表皮角化細胞がもつ機能性の一例であり、すべてを反映しておりません。