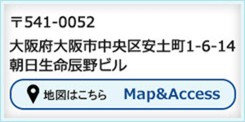016 ヒト組織に代わる実験ツール「三次元培養組織モデル」とは?
2025.10.27
本日は、化粧品業界の研究開発で浸透している「三次元培養組織モデル」を取り上げます。
研究開発の様々なシーンで活用されている!
三次元培養組織モデルは、皮膚に対する安全性試験や、抗老化・美白・保湿・バリアといった有用性評価などに広く活用される、ヒト皮膚に非常に類似した人工のモデルです。
このようにして三次元培養組織モデルは作られる
(EPISKIN社製モデルに関する内容です)
三次元培養組織モデルは、ポリカーボネート製インサートの中で、気液界面培養によって作製されます。
気液界面培養とは、細胞培養面の一方が液体培地に、もう一方が空気に接するようにして細胞を育てる方法です。細胞の表面側が、空気に触れていることで生体に近い構造を再現することができます。
表皮モデルや皮膚全層モデルでは、角質層含む表皮の各層が層構造を形成しています。皮膚全層モデルは、ヒト皮膚同様に、真皮+表皮で構成されています。
表皮・粘膜モデルそれぞれで、ヒト皮膚・粘膜でみられる特異的なタンパク質やマーカーの発現があるため、有用性評価において、ヒト皮膚に非常に類似した構造で、ヒト皮膚を用いるよりも簡単に試験を行うことができるのです。
特に、検体間の有用性の比較や、多検体で実験をする際には、モデルを用いた試験手法がおすすめです。

三次元培養組織モデルの弱点
そんな三次元培養組織モデルにも、弱点があります。
それは、角層の「バリア機能」です。

上の事例は、インドメタシンの累積皮膚透過量を「三次元培養皮膚モデル」と「ヒト摘出皮膚」を用いて比較した事例です。
縦軸の累積皮膚透過量を見ると一目瞭然ですが、ヒト皮膚のバリア機能は非常に高いことが分かります。
構造は、ヒト皮膚に非常に類似していますが、角層バリア機能の再現性は低いという弱点があります。
その点を考慮しつつ、効果的に評価試験に取り入れたいです。
安全性評価への活用
EPISKIN社製の三次元培養組織モデルは、いくつかのOECDテストガイドラインに収載されています。
| モデル | 評価試験 | ガイドライン |
|
表皮モデル SkinEthic™ RHE
|
皮膚一次刺激性試験 | OECD TG439 |
| 皮膚腐食性試験 | OECD TG431 | |
|
角膜上皮モデル SkinEthic™ HCE |
眼刺激性試験 |
OECD TG492 OECD TG492B |
このほかにも、ガイドラインはありませんが、SkinEthic™ HVEを用いて膣粘膜への刺激性を評価するなど、様々な刺激性の評価に活用されています。
眼刺激性試験TG492/TG492Bに関する詳しい情報は、NDRコラム#17「眼刺激性試験 OECD TG492 と OECD TG492Bは何が違う?」もぜひご覧ください。
有用性評価への活用
三次元培養組織モデルは、疑似皮膚として扱えるため、有用性試験にも広く活用されています。
事例をいくつかご紹介いたします。
ー 保湿・バリア評価
SkinEthic™ RHEにサンプルを塗布し、角層膜厚水分計を用いて水分量を測定します。同じモデルを使って、DNAマイクロアレイ(効能ポテンシャル評価)やセラミドやシミ・シワ関連因子を測定することも可能です。

ー 皮膚透過性試験
サンプルをモデルの角層側に添加した後に、モデルおよびリザーバー液を回収し、累積透過量やモデル中量を測り、サンプルの透過量を評価します。
モデルを用いた評価では、ビジュアルで透過量を示したり、多検体での実験、サンプル間での比較をしたりするのに最適です。

ー 美白試験
紫外線照射により黒化する皮膚モデルを用いて、サンプル使用による黒化抑制作用を評価します。結果は、モデルの黒化度合いを目視や色味測定、またメラニン量を測定します。
(※こちらの評価は、試験実施機関作製の組織モデルを使用します)
ー 未熟モデルを用いた評価
通常より短い期間で培養された表皮モデルを用いることで、敏感肌を想定した評価を行うことも可能です。例えば、サンプル使用による水分蒸散量の変化や炎症因子の定量などによる、刺激性評価などです。未熟モデルを用いることで、小さな差を捉えやすいという利点もあります。
ニコダームリサーチはEPISKIN社の国内総代理店です!
当社は、EPISKIN社製モデルの国内総代理店です。
製品に関するご質問やその他お問合せは、問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
モデルのラインナップや、価格、取り扱い情報などは、資料ダウンロードページから資料をダウンロードいただけます。
※貴社名/お名前/ご連絡先を入力いただくと製品資料ページへアクセスいただけます。